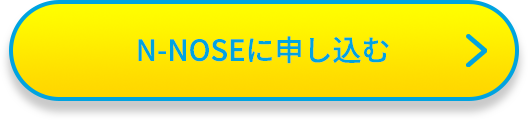線虫がん検査とは?仕組みやメリットなどを解説

線虫がん検査とは?尿でがんリスクがわかる仕組みを解説

線虫がん検査は、生物の嗅覚を活用した次世代のがんスクリーニング検査です。がんの匂いを線虫が感知して、採尿時のがんの可能性を調べられる革新的な検査で近年注目されています。
機械よりも匂いに敏感な生物を活用した検査の仕組みから実際の検査の流れまで、詳しく解説します。
次世代の検査「一次スクリーニング検査」
線虫がん検査は「一次スクリーニング検査」と呼ばれる新しいカテゴリーの検査です。
これまでのがん検査は、5大がん検診やCT、MRIなど部位ごとに調べるものが主流でした。しかし、費用だけでなく身体的負担が大きい検査も少なくありません。そんななか、自覚症状がなくてもまずは入り口の検査としてがんの有無を安価で手軽に調べられる、一次スクリーニング検査が近年注目されています。
がんの一次スクリーニングは新しい概念です。具体的には、自宅にいながら検査できる一次スクリーニングでがんの有無を確認し、高リスクと判定されたら次の段階としてがん種の特定をする二次スクリーニングを受け、さらに医療機関の精密検査でステージを診断される。このように段階的に検査を受けるのが、身体的にも経済的にも負担が少ないがん検査の理想的な流れです。
多忙な日々を送る方でも、痛みなく手軽にがんの有無をチェックできる一次スクリーニングがあれば、がん検査のハードルを大幅に下げられるでしょう。
がんの匂いを線虫が検知してがんリスクを調べる
線虫がん検査の仕組みは、がん患者の尿に含まれる特有の匂い成分を線虫が感知することで成り立っています。
線虫は、好きな匂いには近づき、嫌いな匂いからは遠ざかる特性があります。これは、刺激に対して方向性のある行動(走性)の一つで、線虫は特定の匂いに誘引され、その匂いが存在する方向へ移動する「化学走性」を発現します。
がんには特有の匂いがあると言われており、線虫は尿に含まれるがん特有の匂いを好むので、健康な人の尿であれば線虫は離れていきますが、がん患者の尿なら近づいていく「化学走性」を指標にしたがん検査が線虫がん検査です。
機械よりも匂いに敏感な生物「線虫」
線虫がん検査で使用される線虫(
線虫は本来土壌に生息しているうえ、目や耳がなく匂いを頼りに生きてきたため、嗅覚が非常に発達しています。具体的には線虫は、匂いの分子を認識・キャッチするタンパク質を作るための嗅覚受容体遺伝子を、約1200種類も有しています。
一方で、人間の嗅覚受容体遺伝子は約400種類、犬でも約800種類といわれており、さまざまな場面で匂いを嗅ぎ分けて活躍している犬の1.5倍と考えると、線虫が多くのにおいを識別できると考えられている事がわかるでしょう。
線虫が機械では感知できないごくわずかな匂いも識別できるのは、優れた嗅覚があるからです。
線虫がん検査を受ける流れ
線虫がん検査を受ける流れは非常にシンプルです。
- 1.N-NOSEの公式サイトから検査キットを注文する
- 2.自宅にキットが届いたら、マイページにログイン(初めての人は新規登録)し検査登録をする
- 3.尿を少量採取する
- 4.採取した尿検体を専用の封筒でポストに投函する
- 5.後日、専用WEBページから検査結果を確認する
まずは線虫がん検査のキットを購入して、受検する人の情報をオンラインで登録します。
次に採尿して提出します。自宅で採取した尿は専用封筒を使いポスト投函をするだけで完了します。
提出された尿は、専用の自動解析装置によって繰り返し数十回解析がされます。約4〜6週間後に検査結果がオンラインで確認できるうえ、希望すれば郵送でも通知可能です。
線虫がん検査の特徴とメリット
線虫がん検査には、以下のようなメリットがあります。
・少量の尿で検査が受けられて痛みを感じない
・全身のがんリスクを一括で調べられる
・実社会データでの精度
・がんリスクの早期発見が可能
それぞれの特徴とメリットを詳しく解説していきます。線虫がん検査の特徴を理解すれば、がん検査の入り口として適している理由がわかるでしょう。
少量の尿で検査が受けられて痛みを感じない
線虫がん検査の最大のメリットは、わずかな尿で検査を受けられて痛みがない点にあります。
ほとんどのがん検査は、血液採取による痛みや、内視鏡検査による不快感、痛みがない検査でも放射線検査による被ばくなど、何らかの身体的な負担があります。しかし、線虫がん検査ではわずかな尿を採取できれば調べられるため、採血や注射などの侵襲的な医療行為は必要ありません。
身体的負担がなければ、がん検査に対する心理的なハードルも大幅に下がります。痛みや不快感を理由に検査を避けていた人でも、気軽に受けられるでしょう。
また、検査時間も採尿のみであるため、仕事で忙しい人でも自宅にいながら受検できます。
全身のがんリスクを一括で調べられる
線虫がん検査では、一度の検査で全身のがんリスクを網羅的に評価できる点も大きなメリットです。従来の検査では以下のように部位ごとに検査する必要があります。
・胃がん:バリウム検査や胃カメラ
・肺がん:胸部レントゲンや痰の検査
・大腸がん:便潜血検査・内視鏡検査
・乳がん:マンモグラフィやエコー検査
・子宮頸がん:細胞診
心配な部位ごとに医療機関に行って検査を受けると、時間も費用もかかります。
しかし、線虫がん検査はがんの匂いを嗅ぎ分けるため、全身のがんの可能性を一括で調べられます。特に、死亡数の多い膵臓がんや肝臓がんは5大がん検診では検査できないため、この網羅性は大きなメリットといえるでしょう。
検査を受ける機会が少ない見落としがちな部位のがんを含めて、一括で調べられる線虫がん検査は効率的で経済的負担が少ないといえます。
実用化までに豊富な臨床研究データが蓄積された検査
多くの臨床研究によって蓄積された豊富な検証結果に基づき、N-NOSEは2020年1月に実用化されています。
2024年には1,664名のがん患者を対象とした大規模な臨床試験結果が論文として公表されており、全身20種以上のがんに対して、ステージ0~1の初期のがんであっても感度は70~80%でした。
これらの研究の結果から、N-NOSEによって自覚症状がない初期のがんでも発見できる可能性が高いと示されています。
がんリスクの早期発見が可能
線虫がん検査は、がんの早期発見・治療にも大きく貢献しています。線虫は嗅覚に優れており、極めて微量の匂い成分も感知できる特徴があります。
一般的に、がん細胞がまだ小さい段階では、画像検査や内視鏡検査などで見つけるのは容易ではありません。しかし、線虫なら初期の見つけにくい段階でも反応を示し得るため、従来の検査では発見困難な初期段階、ステージ0〜1のがんの可能性を調べられます。
多くのがん種において、早期に発見されるほど治療の選択肢が広がり、完治率も高くなることが知られています。早期の回復で社会復帰までの期間を短縮できるのも大きなメリットです。
線虫がん検査を定期的に受けると、症状が現れる前の段階でがんの可能性を把握できるため、精密検査後に万が一がんと診断されても、早期に治療を開始できるでしょう。
線虫がん検査の注意点

線虫がん検査には多くのメリットがある一方で、知っておくべき注意点もあります。がん種の特定はできない点、偽陽性・偽陰性の可能性がある点については、正しく理解しておきましょう。
メリットだけでなく注意点も理解しておくと、精神的な不安や追加費用を抑えられます。納得して検査を受けて、その後の健康管理に活かしましょう。
がんの種類は特定できない
線虫がん検査の大きな注意点として、がんの種類や発生部位を特定できない点があります。
線虫は尿中のがん細胞の匂いに反応する特徴はあるものの、胃がんや肺がん、大腸がんなど、どの部位のがんであるかは判別できません。そのため、N-NOSEでは、全身23種のがんの可能性をABCDEの5段階のリスク判定で示しています。
あくまで線虫がん検査はがんの有無を調べる一次スクリーニングです。高リスク判定となった場合には、がん種の特定の二次スクリーニング検査に進むというように、段階的に進めるがん検査の入り口と呼ぶべき検査なのだと認識しておきましょう。
偽陽性・偽陰性の可能性
線虫がん検査も、他の医療検査と同様に偽陽性や偽陰性が発生する可能性があります。偽陽性とは、実際にはがんがないにもかかわらず「がんリスクあり」と判定されることで、偽陰性とは、がんが存在するのに「がんリスクなし」と判定されることです。
線虫がん検査は高い精度を持つものの、他の検査と同様100%完璧な検査ではないと理解しておきましょう。また、感染症や服薬の影響による検査結果への影響は2025年6月時点で不明です。
そのため検査結果にかかわらず、定期的な健康診断を受け続けたり、気になる症状がある場合は医療機関を受診したりするのがよいでしょう。
(参考:『N-NOSEヘルプセンター』)
線虫がん検査と他のがん検査の違い
線虫がん検査は、従来のがん検査とは異なるアプローチを取る検査方法です。
腫瘍マーカーやCT、MRI、内視鏡などはがん種の特定や精密検査として有効であるものの、費用面や身体的負担がかかります。線虫がん検査はがん種の特定はできませんが、全身23種のがんの有無をわずかな尿で検査できます。
まずは、がん検査の入り口として、がんの有無を調べる一次スクリーニングである線虫がん検査を受けて、リスクが高いと判定されたらがん種の特定をする二次スクリーニング、さらに医療機関の精密検査で診断の流れで進めれば、コストや身体的・時間的負担を抑えられます。
それぞれの検査の特性を知って、適切なタイミングで利用しましょう。
線虫がん検査「N-NOSE」でがんのリスクを検査しよう

線虫がん検査は、従来のがん検査と異なる革新的な検査です。がんの匂いを嗅ぎ分ける線虫の性質を利用しており、わずかな尿から全身のがんの可能性を調べられます。
ただし、がん種の特定はできません。そのため、がん検査の入り口となる一次スクリーニングとして役立て、高リスク判定となればがん種の特定のための検査を受けるという流れで活用するとよいでしょう。
線虫がん検査「N-NOSE」は膨大な検体の実社会データに基づいた高い精度を誇ります。「N-NOSE」で、自宅にいながらがんの可能性を検査して早期発見に役立てましょう。