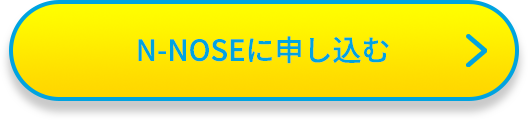がん検査の種類とは?がん検査の理想的な流れと選び方ガイド

がん検診で受けられる検査の種類は?
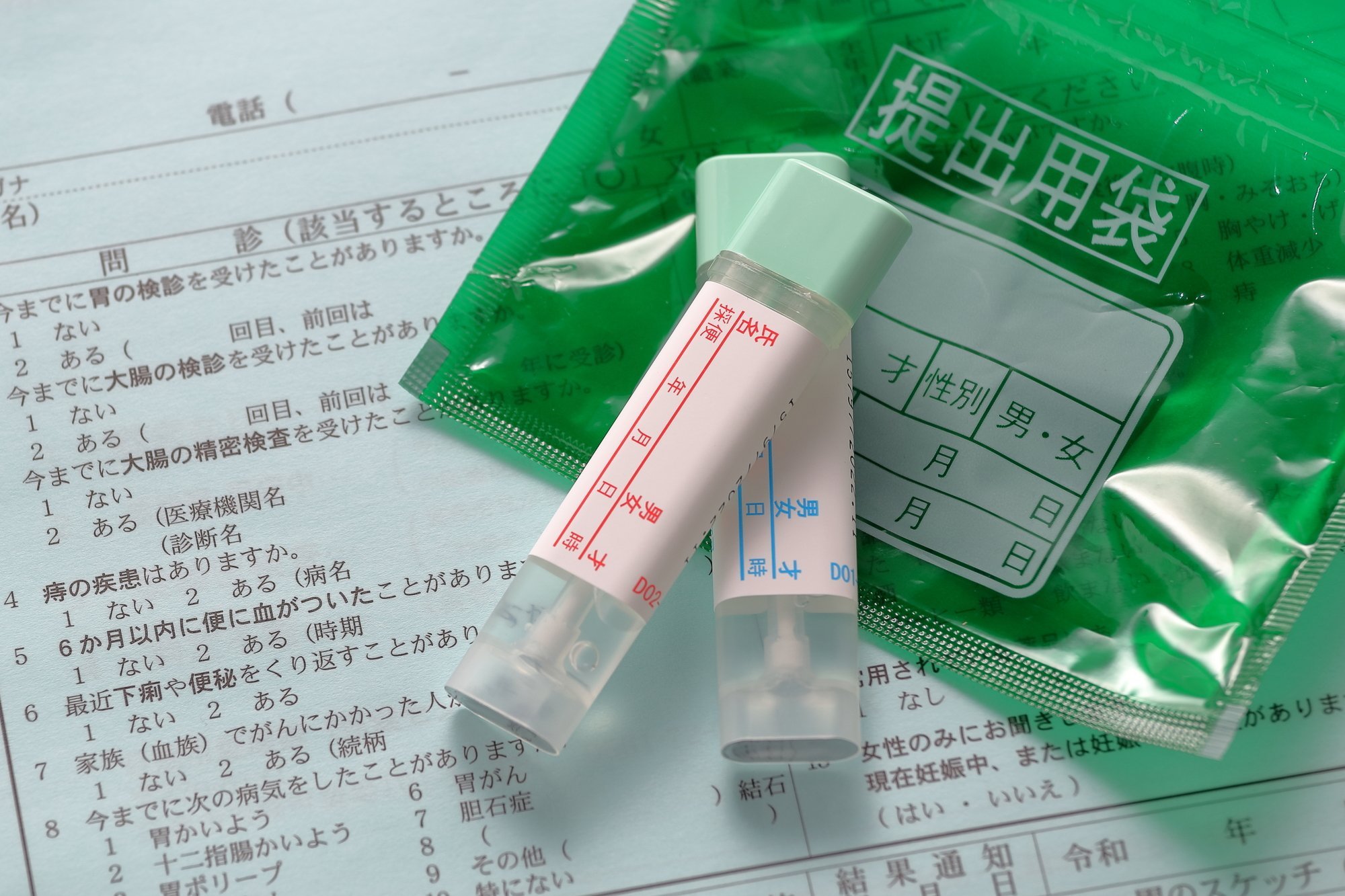
がんの早期発見を目的とするがん検診は、対象となるがん種に応じて適切な検査方法が決まっています。
利益だけでなく不利益もあるため、自分に必要な検診を見極めて適切に選ぶ必要があります。
がん検診の分類
日本のがん検診の分類は、大きく分けて3つです。
まず1つ目は、市区町村などの自治体が住民を対象に実施する住民検診です。公的な制度に基づいて対象年齢や検査内容が定められています。
2つ目は、企業や健康保険組合が従業員や加入者向けに行う職域検診です。基本的に任意で受けるものですが、健康診断に含まれているケースもあります。
国が推奨するがん検診の内容
日本では、がんによる死亡を減らす効果が科学的に明らかになっている5つのがん検診が推奨されています。これらは検査の内容だけでなく、対象者や受診間隔も異なります。
|
|
検査項目 |
対象者 |
受診間隔 |
|
胃がん検診 |
・問診 ・胃X線検査(バリウム検査)または内視鏡検査 |
50歳以上。ただし、胃X線検査は40歳以上も可。 |
2年に1回。ただし、胃X線検査は1年に1回も可。 |
|
大腸がん検診 |
・問診 ・便潜血検査 |
40歳以上 |
1年に1回 |
|
肺がん検診 |
・問診 ・胸部X線検査 ・喀痰細胞診(対象者のみ) |
40歳以上 |
1年に1回 |
|
乳がん検診 |
・問診 ・乳房X線検査(マンモグラフィ) |
40歳以上の女性 |
2年に1回 |
|
子宮頸がん検診 |
・問診 ・視診 ・細胞診 |
20歳以上の女性 |
2年に1回 |
|
・問診 ・視診 ・HPV検査単独法(一部の自治体のみ住民検診で実施) |
30歳以上の女性 |
5年に1回。ただし検査結果によって追跡検査対象者となった場合、1年後に再受診 |
ただし、これらの検診で全身のがんを調べられるわけではありません。たとえば、肝臓がん、卵巣がん、前立腺がんなどは対象外です。
(参考:『子宮頸部:[国立がん研究センター がん統計]』)
(参考:『子宮体部:[国立がん研究センター がん統計]』)
がん検査にはどんな種類がある?

がん検査の種類は多種多様で、それぞれ検出できるがんの種類や精度、費用、体への負担が異なります。
ここでは代表的ながん検査の種類を取り上げ、検査の特徴やメリット・デメリット、おおまかな費用感も解説します。
がん細胞の兆候を数値で知る「腫瘍マーカー検査」
腫瘍マーカー検査は、がん細胞が出す物質(腫瘍マーカー)が血液中にどの程度含まれているか調べる検査です。腫瘍マーカーはがんの種類や臓器によって異なり、代表例には以下のようなものがあります。
・CEA(大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、甲状腺がんなど)
・CA19-9(膵臓がん、胆道がんなど)
・PSA(前立腺がん)
・CA125(卵巣がん、子宮頸がんなど)
採血で調べられるため体への負担が少なく済みますが、腫瘍マーカーはがん以外の病気や生活習慣などの要因でも上昇すると考えられています。また、反対にがんがあっても上昇しない場合もあります。
ホルモン異常からがんを見つける「内分泌検査」
内分泌検査は、血液中に分泌されるホルモンの値を調べる検査です。副腎、甲状腺、膵臓など、ホルモンを分泌する臓器の異常を調べられます。ヨウ素を取り込む甲状腺の性質を利用して甲状腺の大きさや機能を調べる「シンチグラフィ検査」と組み合わせる場合もあります。
ホルモンの値は血液検査や尿検査で調べられるため、体への負担が少なく簡便に行えます。ただし、ホルモンの値は体調や精神的なストレス、性周期など、さまざまな要因の影響を受けて変化するため、ほかの検査との組み合わせが必要です。
スクリーニング検査として行う場合は自由診療となり、一般的には数千円から1万円程度です。
体内を断層で見る「CT(コンピュータ断層撮影)検査」
CT(コンピュータ断層撮影)検査は、さまざまな角度からX線を照射して体を輪切りにしたような画像を撮影する検査です。X線の吸収率の違いから連続した断面図を作成でき、がんの有無や位置だけでなく、大きさや広がり、転移なども調べられます。
さまざまながんの発見に役立つ基本的な検査であり、撮影に伴う痛みはありません。被ばくの量はレントゲン検査よりは多くなりますが、健康に影響を与えない程度の量なので心配しすぎなくてもよいでしょう。
ただし、妊娠中の人や妊娠している可能性がある人は受けられない場合もあります。保険適用であれば、3割負担で6,000円から1万円程度が目安です。
放射線を使わず撮影する「MRI(磁気共鳴画像診断)検査」
MRI(磁気共鳴画像診断)検査は、強力な磁力と電磁波を利用して体内の断面画像を撮影する検査です。
さまざまながんに対して行われ、特に頭部、乳腺、子宮、卵巣、肝臓、前立腺などの検査に有用と考えられています。放射線を使わないため、被ばくのリスクもありません。
一方で、撮影時間はCT検査よりも長く、トンネルのような狭い場所に15分から45分ほど入る必要があります。また、危険防止のためペースメーカーやインプラントなどの体内に埋め込んだ金属がある人や、入れ墨、アートメイクなどをしている人は事前に医師へ伝えましょう。
保険適用で3割負担の場合、5,000円から1万円前後が目安です。
高性能なMRIで全身を調べる「DWIBS検査」
DWIBS検査は、MRIで広範囲のがんを一度に調べる検査です。MRIの高性能化によって検査できる範囲が広くなったことで、短時間の全身MRI検査が実現しました。
一度に全身を調べられるがん検査にはPET検査もありますが、DWIBS検査の方が一般的な検査時間が短い、検査による被ばくがないといったメリットがあります。一方で、通常のMRI検査と同様にペースメーカーを埋め込んでいる人などはDWIBS検査を受けられません。検出しやすいがん種も異なるため、自分に適した方法を選択するのがよいでしょう。
人間ドックなどでスクリーニングとして受ける場合は自由診療となり、全身で5万円から8万円程度が目安です。
がんの活動性を調べる「PET検査」
PET検査は、がん細胞が通常の細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用して、体内のがんの有無や分布を調べる検査です。ブドウ糖に似た性質を持つFDGという薬剤を体内に注射し、どの部位に多く集まっているか撮影します。
全身を一度に撮影できるため、スクリーニングや転移・再発の発見にも役立ちます。特に、頭部や肺、乳腺、大腸、膵臓のがん、血液のがん、悪性黒色腫(メラノーマ)の検査を得意としています。
一方で、1cm未満の小さながんは検出が難しく、脳、心臓、泌尿器、消化器などのブドウ糖が多く集まる部位では正常な組織とがんの見分けがつきにくいなど、弱点もあります。
スクリーニングとして行う場合は自由診療となり、10万円から20万円程度が目安です。
PET(ペット)検査とは?がん発見の仕組みとメリット・費用を解説
がんを調べるPET検査の費用は?保険適用や相場、注意点を解説
体の負担が少ない「超音波(エコー)検査」
超音波(エコー)検査は、体の表面から超音波を当て、その反射を利用して臓器や組織の状態を調べる検査です。痛みや被ばくの心配がないため体への負担が少なく、妊娠している方でも受けられます。
ただし空気や骨は超音波を通しにくいため、肺、骨に覆われた部位(脳など)の検査には適していません。費用は、保険適用であれば数千円程度です。
消化管を直接観察し組織採取も可能「内視鏡検査」
内視鏡検査は、小型カメラがついた細長い管(内視鏡)を体内に挿入し、消化管の内部を観察する検査です。口や鼻から挿入して胃や食道などを調べる「上部消化管内視鏡検査」と、肛門から挿入して大腸を調べる「下部消化管内視鏡検査」があります。
目視で色の変化や細かい凹凸を確認できるため、早期がんの発見も期待できます。さらに、腫瘍を発見したらその場で採取して詳しい検査に回せる点もメリットです。
ただし、内視鏡検査には痛みや苦しさが伴います。検査前の絶食や、下部消化管内視鏡検査の場合は下剤の服用も必要で、身体的・時間的な負担が大きくなりがちです。
検査費用は、保険適用なら3割負担で6,000円から8,000円程度で、生検やポリープの切除などを同時に行う場合はこれよりも高くなります。
乳がんの検査に特化した「乳房X線検査(マンモグラフィ)」
乳房X線検査(マンモグラフィ)は、乳がんの早期発見を目的とした画像検査です。
乳房を薄く圧迫してX線で内部の構造を撮影し、触ってもわからないような小さなしこりや、乳がんの兆候の可能性がある「石灰化病変」の発見も期待できます。
乳がん検診で行うマンモグラフィの費用は自治体や健康保険組合によって異なりますが、無料から千円程度が一般的
唾液や尿などの試料を用いる低侵襲な「リキッドバイオプシー」
リキッドバイオプシーは、唾液や尿などの体液を採取し、その中に含まれているがん細胞やがん細胞由来の物質を解析する検査技術です。がんが疑われる組織を切除する必要がある一般的な生検よりも、体の負担が抑えられます。
リキッドバイオプシーには、以下のような種類があります。
唾液成分から体の変化を探る「唾液検査」
唾液検査は、唾液の成分を分析してがんのリスクを判定する検査です。唾液は血液や尿と同様に、健康状態の指標となるさまざまな物質を含んでいます。
がん細胞が増殖の過程で産生する物質も血液から唾液中に染み出すため、唾液を調べるとがんのリスクが評価できるのです。唾液を自宅などで採取して送るだけなので痛みがなく、時間もかかりません。
ただし、唾液検査でわかるのはがんがある可能性であり、確定診断はできません。唾液検査の結果に応じて、より精密な検査を受ける必要があります。
民間の検査サービスを利用する場合、費用は15,000円から26,000円程度が一般的です。
尿中の微細な物質からリスクを判定する「尿検査」
尿検査には、尿に含まれるがん特有の匂いに反応する線虫の習性を使って採尿時のがんの可能性を評価する検査があります。
線虫の嗅覚は非常に優れており、早期がんのかすかな匂いにも反応します。尿を採取するだけなので痛みがなく、一度の検査で全身のがんの可能性が検査できます。
ただし、尿検査だけで診断できるわけではありません。高リスクと判定された場合、精密検査を受け医師による診察を受ける必要があります。
費用は15,000円程度からと比較的手頃なので、がんの定期的なチェック手段として活用するとよいでしょう。
がん検診は受けるべき?がん検診の受診率

がん検診はがんの早期発見が期待できる有効な検査ですが、全ての人が受診しているわけではありません。がん検診を受ける必要があるのか疑問に思う人もいるでしょう。
この章では、がん検診の受診率や検診を受けるべき理由について解説します。
がん検診の受診率
国立がん研究センターの「がん検診受診率(国民生活基礎調査)」によると、2022年のがん検診受診率は以下の通りです。
・胃がん(40歳から69歳):男性47.5%、女性36.5%
・胃がん(50歳から69歳):男性53.7%、女性43.5%
・大腸がん(40歳から69歳):男性49.1%、女性42.8%
・肺がん(40歳から69歳):男性53.2%、女性46.4%
・乳がん(40歳から69歳):女性47.4%
・子宮頸がん(20歳から69歳):女性43.6%
(参考:『がん検診受診率(国民生活基礎調査による推計値)』)
国では「がん対策推進基本計画(令和5年、第4期)」においてがん検診受診率の目標を60%としていますが、いずれも下回っています。
がん検診は受けるべきか
がん検診には、がんを無症状のうちに発見して早期治療につなげる点など、多くのメリットがあります。検診によって早期発見できれば治療の選択肢が広がり、がんによる死亡リスクを減らせると考えられています。
一方で、がん検診にはデメリットもあります。内視鏡検査やマンモグラフィなどは、痛みや苦しさを理由に受診をためらう人も珍しくありません。
住民検診や職域検診では費用の助成が受けられますが、任意検診の場合は高額になるため金銭的な理由で検診を受けない人もいるでしょう。また、仕事や家庭が忙しいために、時間のかかる検査を受けられない場合もあります。
従って無闇にがん検診を受けるのではなく、自分に合った検診の選び方や理想的な流れを理解したうえで適切にどの検査を受けるか選択するのが重要です。
がん検査の理想的な流れ
時間的・金銭的な負担や痛みががん検診を受けない要因となっているのであれば、まずは一次スクリーニングでがんの有無をチェックする方法もあります。
一次スクリーニングは、自覚症状のない一般の人々を対象として、尿検査などの方法で広く全身のがんの可能性を調べる方法です。その結果に応じて、PET検査などの二次スクリーニング検査でがん種を特定し、さらに次のステップとして医療機関で精密検査を受ける流れが、身体的・経済的な負担も少なく理想の流れといえます。
一次スクリーニングで高リスク判定を受けた場合は放置せず、早めに精密検査を受けましょう。
\ N-NOSEで全身23種のがんリスクをチェック! /
がん検査の選び方のコツ

がんの検査には多くの種類があり、近年では一次スクリーニングのような新しい方法も登場しています。適切な検査を選べるよう、コツを押さえておきましょう。
がん検査の選び方
がん検査を選ぶ際は、科学的根拠に基づいているかどうかを確認しましょう。
科学的根拠が確立された検査とは、実際に多くの人に対して実施し、効果が研究結果や公表データに裏づけられている検査を指します。「有名な医師が推奨している」「新しい技術を取り入れている」といった説明だけでは、検査の信頼性を判断する材料としては不十分です。
特に、新しい技術を活用した検査の中には、理論を明らかにするための基礎研究や、まだ臨床試験や治験に至っていない臨床研究の段階である検査もあります。実社会での活用データが十分そろっているかどうかも、検査を選ぶ重要なポイントの一つです。
がん検査の正しい知識を持って、がんの早期発見につなげよう!
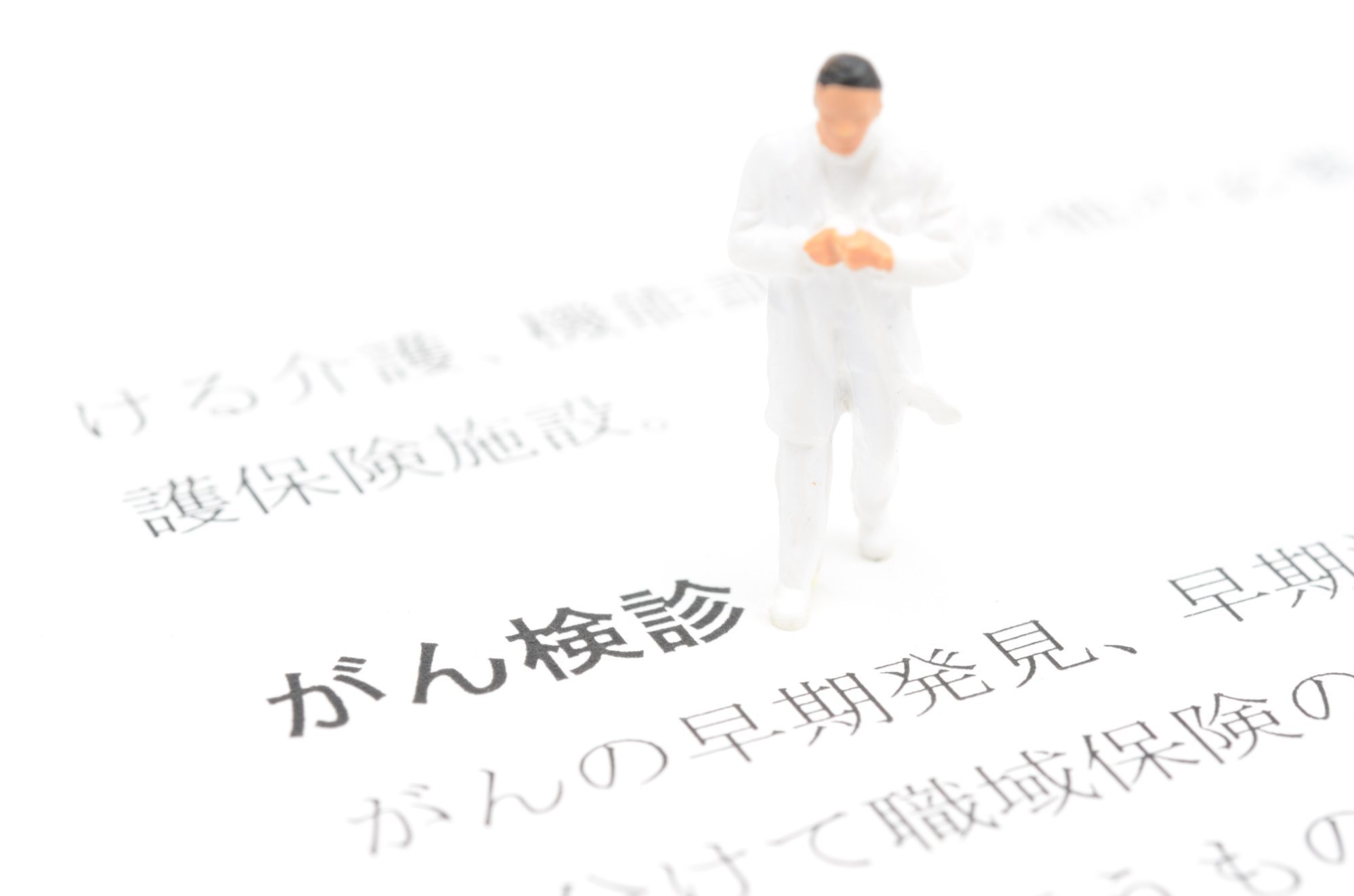
がんの検査には多くの種類があり、それぞれに特徴や役割の違いがあります。費用や所要時間も踏まえて、自分のニーズに合った検査を受けることが重要です。
どの検査にもメリット・デメリットがあり、精度は100%ではありません。複数の検査を組み合わせて定期的に受診し、がんの早期発見につなげましょう。