
「動けること」が、
人生を支える。
ブルーデニム軽井沢 代表
谷川 靖子
Chapter 1 / 健康寿命とテニスの関係

テニスクラブ「ブルーデニム軽井沢」を開設される前は、看護師として地域医療に携わっていたそうですが、なぜテニスクラブを作ろうと思ったのですか?
私が地域医療の世界に足を踏み入れた頃、ちょうど国は団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に力を入れていました。その中で私は看護師として、ご高齢の方々や、まだ若くしてがんなどの病気と闘う方など、住み慣れた自宅で最後まで過ごしたいと希望される多くの方々を支援してきました。
しかしその一方で考えさせられたことは、今は私たち団塊の世代ジュニアの人口比率が高く、こうして手厚い医療・介護の支援を行うことができるものの、「私たちが高齢者になった時はどうなのか?」ということでした。
奇しくも今年は2025年です。団塊の世代(1947~49年生)が75歳以上となり、高齢者の人口増加が始まる超高齢化社会がスタートする年です。高齢者の人口増加は2054年まで続くと予測されています。2040年には団塊の世代ジュニア(1971~74年生)が65歳を超え、高齢者人口が増えることに加えて、少子化による現役世代の急激な減少が重なり、社会保障費の増大や労働力不足も深刻になってきます。社会保障費の中でも医療・介護費の増大幅は大きく、現役世代の減少は医療・介護に携わる人の人手不足にも拍車をかけることになるでしょう。
2054年には、増え続けた75歳以上の高齢者が全人口の25%に達し、4人に1人が75歳以上というさらなる超々高齢化社会を迎えると予測されています。私は1973年に生まれた団塊ジュニアど真ん中です。2040年に67歳、2054年には81歳になります。どんな人にも例外なく、自身の高齢化は確実にやってきます。
もちろんAIやロボットなどの技術が進化し、急速な少子高齢化を支える力になってくれるかもしれません。しかし何よりも私たちが健康に年を取ることが重要だと思うようになりました。社会のためだけでなく、自分たちもその方が幸せですよね。
私は、いつか「健康に年を取る」ための活動をしたいと思うようになりました。その活動フィールドとして選んだのがテニスクラブだったのです。
しかしその一方で考えさせられたことは、今は私たち団塊の世代ジュニアの人口比率が高く、こうして手厚い医療・介護の支援を行うことができるものの、「私たちが高齢者になった時はどうなのか?」ということでした。
奇しくも今年は2025年です。団塊の世代(1947~49年生)が75歳以上となり、高齢者の人口増加が始まる超高齢化社会がスタートする年です。高齢者の人口増加は2054年まで続くと予測されています。2040年には団塊の世代ジュニア(1971~74年生)が65歳を超え、高齢者人口が増えることに加えて、少子化による現役世代の急激な減少が重なり、社会保障費の増大や労働力不足も深刻になってきます。社会保障費の中でも医療・介護費の増大幅は大きく、現役世代の減少は医療・介護に携わる人の人手不足にも拍車をかけることになるでしょう。
2054年には、増え続けた75歳以上の高齢者が全人口の25%に達し、4人に1人が75歳以上というさらなる超々高齢化社会を迎えると予測されています。私は1973年に生まれた団塊ジュニアど真ん中です。2040年に67歳、2054年には81歳になります。どんな人にも例外なく、自身の高齢化は確実にやってきます。
もちろんAIやロボットなどの技術が進化し、急速な少子高齢化を支える力になってくれるかもしれません。しかし何よりも私たちが健康に年を取ることが重要だと思うようになりました。社会のためだけでなく、自分たちもその方が幸せですよね。
私は、いつか「健康に年を取る」ための活動をしたいと思うようになりました。その活動フィールドとして選んだのがテニスクラブだったのです。


「ブルーデニム軽井沢」は、“今テニスを楽しむ私たちが、70代、80代になってもテニスを楽しむ”ことを目標にされていますね。クラブを運営する中で、健康に対するお客様の意識の変化を感じますか?
結論からいうと、確実に変化は感じます。
現在、行っている取り組みは、「大人の体力測定」と「N-NOSE検査」を年2回推奨することです。クラブ開設1周年にあたる1年前から始めました。今の体力を維持して元気にテニスを楽しみ続けること、日本人の死因第1位であるがんを早期発見することが、健康に年を取るために重要不可欠だと考えたからです。
体力測定はただ測定するだけでなく、前回よりも低下した測定項目や怪我の予防、日頃の故障の悩みなどに対して、パーソナルトレーナーが個別にサポートしています。みなさん始めた当初はピンとこない感じでしたが、「いくつになってもテニスを楽しみたいですよね?」「今日の体力が半年後の目標ですよ」と、測定の目的を単純で共感しやすくしたことで、意識も変化してきたのだと思います。また65歳以上の現役プレーヤーたちが、平気で若者顔負けの結果を叩き出すのも刺激になっています。
40代~50代の人たちにとって「あんな風に年を取りたい」と思える身近なモデルの存在はいいことだと思います。今では体力測定は定着し始め、N-NOSEも多くの方が受検しています。今後、もっと増えていくと思います。
現在、行っている取り組みは、「大人の体力測定」と「N-NOSE検査」を年2回推奨することです。クラブ開設1周年にあたる1年前から始めました。今の体力を維持して元気にテニスを楽しみ続けること、日本人の死因第1位であるがんを早期発見することが、健康に年を取るために重要不可欠だと考えたからです。
体力測定はただ測定するだけでなく、前回よりも低下した測定項目や怪我の予防、日頃の故障の悩みなどに対して、パーソナルトレーナーが個別にサポートしています。みなさん始めた当初はピンとこない感じでしたが、「いくつになってもテニスを楽しみたいですよね?」「今日の体力が半年後の目標ですよ」と、測定の目的を単純で共感しやすくしたことで、意識も変化してきたのだと思います。また65歳以上の現役プレーヤーたちが、平気で若者顔負けの結果を叩き出すのも刺激になっています。
40代~50代の人たちにとって「あんな風に年を取りたい」と思える身近なモデルの存在はいいことだと思います。今では体力測定は定着し始め、N-NOSEも多くの方が受検しています。今後、もっと増えていくと思います。


テニスはどのような形で健康寿命延伸に役立っているとお考えですか?
テニスは健康寿命を延ばすスポーツとして非常に優秀であることが、世界各国で発表されている多くの研究によって明らかにされています。スポーツをしない人と比べると、平均寿命が約10年長く、死亡率は47%減、とりわけ心血管疾患による死亡率は56%減、さらに、生活習慣病のリスクも低下させるという驚きの結果が出ています。運動強度が適度であるとか、コミュニティが活発な社会的スポーツであるとか、ゲーム性が高く、戦略的思考や瞬時の判断力が求められるため、認知機能の維持・向上にも役立っている可能性があるなど、テニスが健康寿命を延ばす理由は様々に推測されていますが、何が理由であれ、テニスを通じて、仲間と笑い、楽しく元気に年をとることができるのなら、それはとても素晴らしいことだと思います。
参考:2017年 アメリカテニス事業協会(TIA)がまとめた「テニスをすべき10の理由」
出典:公益社団法人日本テニス事業協会
ただ、このようにテニスは健康寿命の延伸に大いに役立つスポーツだと思いますが、この驚くべき健康効果についての認知度は高くないように思います。テニスの健康効果を広く一般の方に知っていただき、テニスを始めてみる人や楽しむ人が増えて、初めて「テニスが健康寿命の延伸に役立てる」と言えるのではないのでしょうか。
もともと運動をしない人が、「運動習慣を獲得する」ことは簡単ではありません。ウォーキングやジム通いなどは、ひとりでも手軽に始めやすい運動ですが、続けられない人が多いのも事実です。それに対し、テニスは全国各地で様々なレベル・年齢別の大会が豊富に開かれており、年齢を問わないテニスの継続性と技術向上へのモチベーションを生んでいます。実際に、ベテランプレーヤーとして目標をもってテニスをされている方はもちろん、仲間との交流を楽しみにテニスをされる方まで、継続の原動力はテニスの楽しさです。今まで健康のために運動を続けられなかった人には、ぜひ対人スポーツでゲーム性が高く、「最も健康的なスポーツ」と言われるテニスをお勧めしたいです。
参考:2017年 アメリカテニス事業協会(TIA)がまとめた「テニスをすべき10の理由」
出典:公益社団法人日本テニス事業協会
ただ、このようにテニスは健康寿命の延伸に大いに役立つスポーツだと思いますが、この驚くべき健康効果についての認知度は高くないように思います。テニスの健康効果を広く一般の方に知っていただき、テニスを始めてみる人や楽しむ人が増えて、初めて「テニスが健康寿命の延伸に役立てる」と言えるのではないのでしょうか。
もともと運動をしない人が、「運動習慣を獲得する」ことは簡単ではありません。ウォーキングやジム通いなどは、ひとりでも手軽に始めやすい運動ですが、続けられない人が多いのも事実です。それに対し、テニスは全国各地で様々なレベル・年齢別の大会が豊富に開かれており、年齢を問わないテニスの継続性と技術向上へのモチベーションを生んでいます。実際に、ベテランプレーヤーとして目標をもってテニスをされている方はもちろん、仲間との交流を楽しみにテニスをされる方まで、継続の原動力はテニスの楽しさです。今まで健康のために運動を続けられなかった人には、ぜひ対人スポーツでゲーム性が高く、「最も健康的なスポーツ」と言われるテニスをお勧めしたいです。


看護師としての経験が、クラブ運営や健康支援にどのように活かされていますか?
看護師としての経験とテニスというスポーツを融合させることで、予防医療や健康増進の場を創出し、効果的に提供できるのではないではないかと考えています。
たとえば、医療介護のよろず相談窓口の役割です。健康診断結果の相談から、小さな体調不良、病院を受診した方がいいのかなど、自分や家族の健康、あるいは親の介護の悩みまで、私が相談を受ける機会は多くあります。これは、「テニスのついで」という気軽さから小さな不安でも聞いてみようという気になるからだと思います。行政や病院などの窓口に相談に行くには、具体的に深刻な困りごとを抱えているなどの「原動力」が必要です。気にかかる程度、まだ頑張れるうちには、なかなか相談には行けないものです。地域医療の現場にいた時には、相談に来る時には限界が近い状態のことも多く、何度も「もっと早く相談してもらえたら」と思っていました。そのため「日常から手の届くところに相談できる場所がある」という今の環境は、かつて描いていた理想的な相談窓口の在り方だと思っています。
もうひとつは救急対応の役割です。熱中症や怪我があれば、すぐに対応してもらえるという安心感はあると思います。さらに、コートで誰かが倒れるなど「いざ」という時には、仲間の命を救いたいと誰もが思っています。私は看護師ですが、クラブには医師の会員さんもいますので、専門的な知識を持つ医療者を中心に、会員の皆さんにテニス中における緊急事態に備えて、積極的に救急講習を受けていただくような活動も行っています。
将来的には、体力測定・N-NOSE・医療介護のよろず相談窓口を、地域の方々にも利用してもらえるような仕組みを構築し、テニスクラブが地域の健康拠点になれることを目指していきたいと思っています。
たとえば、医療介護のよろず相談窓口の役割です。健康診断結果の相談から、小さな体調不良、病院を受診した方がいいのかなど、自分や家族の健康、あるいは親の介護の悩みまで、私が相談を受ける機会は多くあります。これは、「テニスのついで」という気軽さから小さな不安でも聞いてみようという気になるからだと思います。行政や病院などの窓口に相談に行くには、具体的に深刻な困りごとを抱えているなどの「原動力」が必要です。気にかかる程度、まだ頑張れるうちには、なかなか相談には行けないものです。地域医療の現場にいた時には、相談に来る時には限界が近い状態のことも多く、何度も「もっと早く相談してもらえたら」と思っていました。そのため「日常から手の届くところに相談できる場所がある」という今の環境は、かつて描いていた理想的な相談窓口の在り方だと思っています。
もうひとつは救急対応の役割です。熱中症や怪我があれば、すぐに対応してもらえるという安心感はあると思います。さらに、コートで誰かが倒れるなど「いざ」という時には、仲間の命を救いたいと誰もが思っています。私は看護師ですが、クラブには医師の会員さんもいますので、専門的な知識を持つ医療者を中心に、会員の皆さんにテニス中における緊急事態に備えて、積極的に救急講習を受けていただくような活動も行っています。
将来的には、体力測定・N-NOSE・医療介護のよろず相談窓口を、地域の方々にも利用してもらえるような仕組みを構築し、テニスクラブが地域の健康拠点になれることを目指していきたいと思っています。

Chapter 2 / 予防医療とN-NOSEの可能性

HIROTSUバイオサイエンスのN-NOSEを知ったきっかけと、最初に感じた印象は?
初めてN-NOSEを知ったのはTVで流れていた線虫くんのCMでした。がんのスクリーニング検査として画期的だと衝撃を受けたのを覚えています。尿だけでがんのリスクを調べられたらすごいなと。私は看護師として、がんで命を落とす人をたくさん見てきました。がんの早期発見が出来ていれば、と思い浮かぶ顔もたくさんあります。それだけに、全身のがんのリスクを調べることができる検査の登場に、当時の私は大変興奮しました。
従来のがん検診は高額ですし、苦しい検査もありますし、そもそもがんになるなんて他人事だと思っている人も多いですから、なかなか普及しません。しかしリスクがわかれば検査を受ける気にもなります。時間的にも費用的にもとても効率的だと思いました。
従来のがん検診は高額ですし、苦しい検査もありますし、そもそもがんになるなんて他人事だと思っている人も多いですから、なかなか普及しません。しかしリスクがわかれば検査を受ける気にもなります。時間的にも費用的にもとても効率的だと思いました。


中高年層が“がん検診”に消極的になる理由として、どのような要因があると思いますか?
要因は大きく4つあるのではないかと思います。1つ目は心理的な恐怖感です。「悪い結果が出るかもしれない」という不安、検査の不快感や痛みなどへの不安です。2つ目には、仕事を休めない、検診のための時間が取れない、検診費用が高いといった、時間的・経済的な負担です。そして3つ目は、知識や認識の問題だと思います。自覚症状がないため必要性を感じない、あるいは「自分は大丈夫」という根拠のない自信などがそうです。その他は、検診施設までの距離や予約の取りにくさ、情報へのアクセスの難しさなどをまとめて、検診を「面倒くさい」と感じること。これが4つ目の要因になるのではないかと思います。


N-NOSEの“手軽さ”や“非侵襲性(痛みのない検査)”が、検診のハードルを下げると感じられますか?
N-NOSEの“手軽さ”と“非侵襲性”は、従来の検査における時間的制約、痛みや不快感、心理的抵抗といったハードルを大きく下げると思います。さらに16,800円という検査費用は、圧倒的なコストパフォーマンスだと思います。これらは先に述べた「中高年層が“がん検診”に消極的」になる理由のほとんどを解決してくれます。
そうなると、あとは「検査結果への心理的な恐怖感」と「検診の必要性を感じる知識や認識の問題」です。もしかしたらハードルの中で一番高いところかもしれません。
しかしN-NOSEの“手軽さ”は、この問題に対しても効果があり、ハードルを下げる可能性があると思っています。「結果を知るのがこわい」という心理に対しては、検査結果があくまでリスク判定で確定診断ではないところや、携帯やPCから好きなタイミングで、ひとりで確認できることが、病院に検査結果を聞きに行くよりも心理的な恐怖心を和らげることが期待できます。さらに、N-NOSEの“手軽さ”のおかげで、検査を受けた人はどんな検査かを周囲に説明したり、一緒に受けてみようと誘いあったりすることを可能にします。これは実際、ブルーデニムでN-NOSEを受けた人たちの間でも普通にみられる光景です。このように“手軽さ”と“非侵襲性”が受検者を増やし、そのことが2次的に周囲の人の心理的な検診のハードルを下げることにつながるのではないでしょうか。
そうなると、あとは「検査結果への心理的な恐怖感」と「検診の必要性を感じる知識や認識の問題」です。もしかしたらハードルの中で一番高いところかもしれません。
しかしN-NOSEの“手軽さ”は、この問題に対しても効果があり、ハードルを下げる可能性があると思っています。「結果を知るのがこわい」という心理に対しては、検査結果があくまでリスク判定で確定診断ではないところや、携帯やPCから好きなタイミングで、ひとりで確認できることが、病院に検査結果を聞きに行くよりも心理的な恐怖心を和らげることが期待できます。さらに、N-NOSEの“手軽さ”のおかげで、検査を受けた人はどんな検査かを周囲に説明したり、一緒に受けてみようと誘いあったりすることを可能にします。これは実際、ブルーデニムでN-NOSEを受けた人たちの間でも普通にみられる光景です。このように“手軽さ”と“非侵襲性”が受検者を増やし、そのことが2次的に周囲の人の心理的な検診のハードルを下げることにつながるのではないでしょうか。


医療従事者(看護師)として、N-NOSEの医療現場や地域予防活動での可能性についてどう見られていますか?
N-NOSEは地域の予防医療活動における教育・啓発ツールとして、大いに活用が期待できると思います。自覚症状がないため検診の必要性を感じない、あるいは「自分は大丈夫」という根拠のない自信など、知識や認識の問題があると述べましたが、N-NOSEのような“手軽さ”と“非侵襲性”は、地域の予防医療プログラムに組み込むことを可能にしますし、住民の健康意識向上と早期発見率の向上に貢献する可能性があるのではないでしょうか。特に30〜60代のがんリスクを気にする層にとって重要な選択肢となり、がんを早期発見する意義を伝える手段として活用することができると思います。
今後は高リスク判定後の精密検査や治療へのスムーズな移行を可能にする連携体制がさらに整備されていけば、N-NOSEは包括的ながん予防・早期発見システムの一部へと発展していくのではないでしょうか。
また、郵送が可能となった検体の提出システムは、医療資源の地域格差を超えて予防医療を実現する可能性もあると思います。特に医療機関へのアクセスが限られた地域や、高齢化が進む地域において、自宅で実施できる検査は大きな意義を持つのではないでしょうか。
今後は高リスク判定後の精密検査や治療へのスムーズな移行を可能にする連携体制がさらに整備されていけば、N-NOSEは包括的ながん予防・早期発見システムの一部へと発展していくのではないでしょうか。
また、郵送が可能となった検体の提出システムは、医療資源の地域格差を超えて予防医療を実現する可能性もあると思います。特に医療機関へのアクセスが限られた地域や、高齢化が進む地域において、自宅で実施できる検査は大きな意義を持つのではないでしょうか。

Chapter 3 / 今後の展望とメッセージ

運動・食事・検診など、健康長寿のために最も大切だと考えることは何ですか?
一般的に、健康長寿を実現するためには、運動・食事・検診などの要素をバランスよく組み合わせた総合的なアプローチが重要だと言われています。もちろん、それは正しいことだと思いますし、厚生労働省の健康施策においても、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」という複数の視点から取り組まれています。
私はその中でも、「社会環境の質の向上」が健康長寿のためにはとても重要だと感じています。地域あるいは趣味のコミュニティにおける支え合いや社会参加の機会を確保すること、いくつになっても社会とつながりを持ち続けることは、精神的な健康を維持する上で大変重要な要素です。年齢に関係なく、「毎日が楽しいこと」・「笑いあえる仲間がいること」は幸せです。もちろん身体的な健康が基盤ですが、社会的な健康こそが、運動・食事・検診などの身体的な健康行動を支えることにもつながり、健康長寿に最も欠かせない要素なのではないかと思っています。
私はその中でも、「社会環境の質の向上」が健康長寿のためにはとても重要だと感じています。地域あるいは趣味のコミュニティにおける支え合いや社会参加の機会を確保すること、いくつになっても社会とつながりを持ち続けることは、精神的な健康を維持する上で大変重要な要素です。年齢に関係なく、「毎日が楽しいこと」・「笑いあえる仲間がいること」は幸せです。もちろん身体的な健康が基盤ですが、社会的な健康こそが、運動・食事・検診などの身体的な健康行動を支えることにもつながり、健康長寿に最も欠かせない要素なのではないかと思っています。


今後、HIROTSUバイオサイエンス社に期待することや、協働してみたい取り組みがあれば教えてください。
HIROTSUバイオサイエンス社のN-NOSEの“手軽さ”と“非侵襲性”は、がんの一次スクリーニング検査として、今後も医療現場や地域予防活動において、従来のがん検診を補完し、より多くの人々が早期発見の恩恵を受けられる可能性を秘めていると思います。医療機関との広範な連携、教育・啓発活動への活用、地域医療における予防医療の一環としての位置づけなど、多面的により多くの人々の健康長寿に貢献していただくことを心から期待しています。
協働してみたい取り組みは、テニスの健康効果とN-NOSEの組み合わせをもっと多くの人に広めるために、イベントの共同開催などができたら嬉しいです。今もクラブのイベントに協賛していただいていますが、もっともっと大きな規模で開催出来たらいいですね。日本人の死因第1位のがんはN-NOSEで早期発見できる可能性がありますし、死因第2位の心疾患はテニスでそのリスクを軽減できると言われていますので、この組み合わせは健康寿命の延伸にとても効果的だと思っています。テニス業界はテニスプレーヤーにN-NOSEを活用した健康意識の向上を働きかけ、HIROTSUバイオサイエンス社はN-NOSEを利用している運動習慣のない人にテニスの健康効果をお伝えする。そんな風に今後も協力し合えたら素晴らしいなと思います。
協働してみたい取り組みは、テニスの健康効果とN-NOSEの組み合わせをもっと多くの人に広めるために、イベントの共同開催などができたら嬉しいです。今もクラブのイベントに協賛していただいていますが、もっともっと大きな規模で開催出来たらいいですね。日本人の死因第1位のがんはN-NOSEで早期発見できる可能性がありますし、死因第2位の心疾患はテニスでそのリスクを軽減できると言われていますので、この組み合わせは健康寿命の延伸にとても効果的だと思っています。テニス業界はテニスプレーヤーにN-NOSEを活用した健康意識の向上を働きかけ、HIROTSUバイオサイエンス社はN-NOSEを利用している運動習慣のない人にテニスの健康効果をお伝えする。そんな風に今後も協力し合えたら素晴らしいなと思います。


発明から10年を迎えるHIROTSUバイオサイエンス社へのメッセージをお願いします。
N-NOSEの発明から10周年を迎えられたこと、心よりお祝い申し上げます。広津崇亮代表が線虫の持つ驚異的な嗅覚能力に着目し、がんの早期発見という課題に挑戦し続けてこられた10年間の歩みに深い敬意を表します。
ホームページのトップに流れる「常識」の先を行く-という言葉。前例のない領域に挑戦し続けるには、大きなエネルギーが必要だと思います。原動力は、単なる技術開発ではなく「がんで苦しむ人をなくしたい」「N-NOSEを一人でも多くの人に提供したい」という揺るぎない信念なのだと感じます。
これからの10年も、人々の健康と幸せに貢献する革新的な取り組みで、社会に大きなインパクトを与え続けていただきたいと思います。

PROFILE
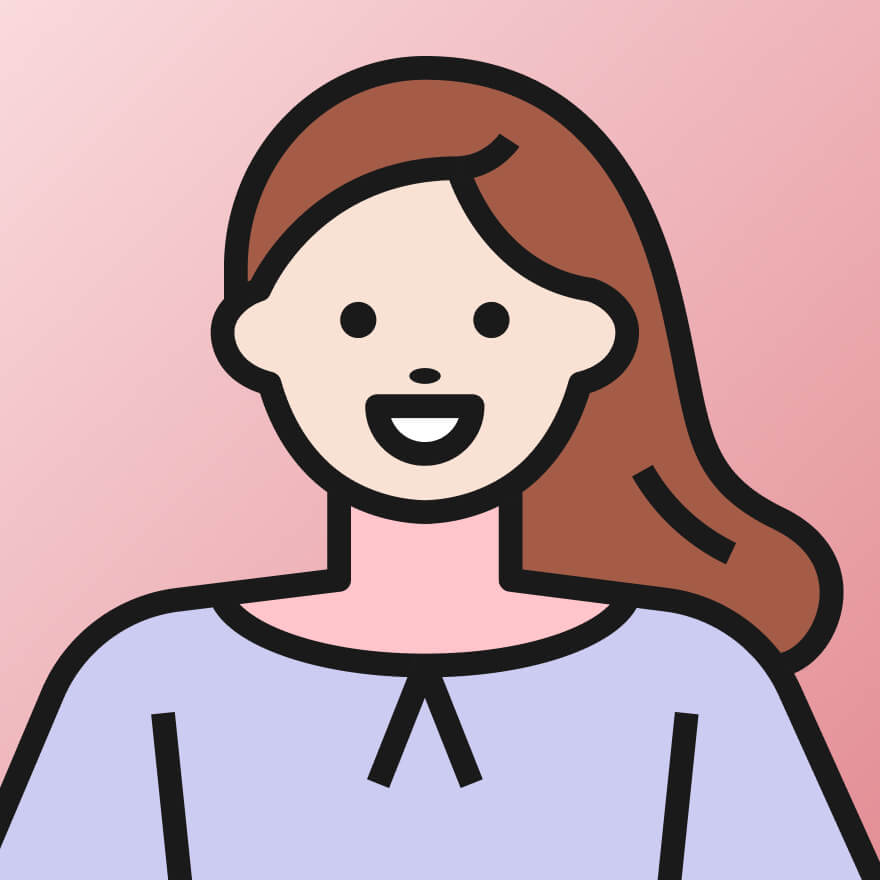

ブルーデニム軽井沢 代表
谷川 靖子
- PROFILE -
テニスを生涯スポーツとして楽しめる環境を提供することを目指す理念は、「今テニスを楽しむ人たちが、70代、80代になっても元気にテニスを楽しむ。いくつになっても、上手くなりたいを応援する。」というもので、年齢を問わず、テニスを楽しむすべての人々を応援しています。
